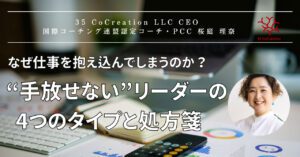社員のエグゼクティブプレゼンスを高めるたった一つの方法
コーチングリーダーシップ人材開発2024年12月16日
今回は、組織サーベイについての投稿第2弾です。組織や社員の課題を可視化する上で、サーベイは効果的なツールです。しかし、同じ評価項目であっても、その背景や文脈は人それぞれ異なり、時には深い理解や考察が必要です。 前回はサーベイに隠された社員の本音についてお話しましたが、本記事では、サーベイ結果の中でも特に改善に悩むことが多い「エグゼクティブプレゼンス」に焦点を当て、抽象度の高い評価結果から具体的な改善策につなげるための有効な方法を解説します。 エグゼクティブプレゼンスという「呪い」 コーチングにおいて、受講者から最も多く寄せられる課題の一つが、「エグゼクティブプレゼンスが低い」という悩みです。 人事評価で用いられることの多い360度サーベイで、エグゼクティブプレゼンスが低いと評価されると、多くの場合、「このままでは昇進は難しい」という判断を下されがちです。そのため、昇進を望む人たちは、エグゼクティブプレゼンスを高めるために必死になり、「自分はエグゼクティブプレゼンスがないからダメなんだ」と自信を失ってしまう人も少なくありません。 ではそもそも、『エグゼクティブプレゼンス』とは一体何なのでしょうか。「上に立つ人に求められる資質」「一流の存在感」とも訳されるこの言葉。一言で定義することは難しく、明確に答えられる人は、まずいないでしょう。捉えどころのない概念だからこそ、多くの人がエグゼクティブプレゼンスの呪縛に囚われているといえます。(私も実際、過去に自身のエグゼクティブプレゼンスが低いと評価された経験があり、形のない“ゴースト”に縛られ、苦しみました) 『エグゼクティブプレゼンス』という言葉に対する捉え方は、実に人それぞれ。 例えば、「発言量が少ない」だったり、「反対意見に対して自分の考えを明確に示せていない」だったり、エグゼクティブプレゼンスが低いとされる要因には様々な可能性があり得ます。 360度サーベイでは上司、同僚、部下、それぞれが異なる視点からこの言葉の意味を解釈しているため、まずはその多様な解釈を整理することがコーチングの最初のステップとなります。 涙のプレゼンターがグローバルリーダーに昇格するまで ここで一つ、エグゼクティブプレゼンスにちなんだ具体的な事例をご紹介します。 会社員のアキコさん(仮名)は、プレゼンなどで緊張すると涙が出てしまうという傾向がありました。プレッシャーを感じると呼吸が浅くなり、酸素不足で涙が出てしまう体質だったのです。英語でのプレゼンテーションでは、特にこの傾向が顕著でした。彼女は自分の考えを正確に伝えたいという強い気持ちから、極度の緊張状態に陥り、呼吸が浅くなることで涙が出てしまうのです。 しかし周囲からは、それが感情的な弱さだと認識され、すなわちリーダーになるべき立場としてはエグゼクティブプレゼンスが欠如していると捉えられていました。 彼女は、「ごめんなさい、これはちょっと体の反応なんです」と説明すればよかったのですが、周囲が勝手に「アキコさんはすごくつらいんだな」「プレッシャーに弱いんだ」と解釈し、そのフィードバックを繰り返すことで、アキコさん自身も「私はやっぱりプレッシャーに弱いから泣いちゃうのかもしれない」「やっぱりこういう場面でうまくできないから私はダメなのよね」と、次第にそう思い込んでしまったのです。 コーチングを通して、彼女は自分の意図と周囲の受け取り方の間に大きなギャップがあることに気づきました。何度かのセッションを通じて、体の反応を事前に察知しコントロールすることで、周囲の誤解を解けることに気づいた彼女は、呼吸法などのトレーニングを重ね、緊張を克服しました。その結果、アキコさんは、大規模なグローバルプロジェクトのリーダーとして活躍し、見事成功を収めることができました。 この事例からもわかるように、エグゼクティブプレゼンスは、様々な要素が複雑に絡み合ったものです。そのため、エグゼクティブプレゼンスを高めるためには、個々の状況を深く理解し、一人ひとりに合ったアプローチを選ぶことが求められます。 しかし、アンケート調査などでは、エグゼクティブプレゼンスのどの部分が問題となっているのか、具体的に特定するのが難しいことが多いです。例えば、「決断が遅い」「コミュニケーションが不十分」といった項目と、エグゼクティブプレゼンスの項目、どちらにも指摘があると、それらと関連付けられることがあります。 しかし実際にコーチングを通じてより深いレベルでの対話をしていくと、まったく別のところに、原因が判明することがあります。 特に、エグゼクティブプレゼンスのように、捉え方が人によって異なる抽象的な概念については、しっかり対話しながら、その人ならではの状況や背景を深く理解することが重要です。そうすることで、その人が抱える「見えない壁」を可視化し、具体的な解決策へと繋げていくことができるのです。 アキコさんのケースでは、自分の涙が生理的な反応であることを認められたことで、周囲の評価に振り回されることなく、自分自身を受け入れることができるようになりました。 その後の彼女が素晴らしかったのは、緊張で涙をこらえている自分と同じような人の存在に気づき、重要な会議の前に「まずちょっといいですか、みんなで深呼吸をしましょう」と提案したそうなんです。「今日すごく重要な局面で私も緊張してるので、皆さんも1回立ってストレッチして深呼吸しましょう」と。この行動は、グローバルなミーティングでも高く評価され、結果的に彼女を昇格させたのでした。 エグゼクティブプレゼンスを高めるたった一つの方法 アキコさんは、コーチングの中でこれまで心の奥底に隠していた傷や弱みを素直に打ち明け、自己と向き合いました。その結果、自己肯定感が大きく高まり、その心の余裕が周囲への行動に現れ、エグゼクティブプレゼンスの向上にも繋がりました。 アキコさんは、コーチングの経験を「癒された」と表現します。私たちは日常的に様々な評価に晒されていますし、特に仕事においては常にジャッジの対象。コーチングは、そんな日常から離れ、自分自身と向き合う貴重な時間です。アキコさんのように、コーチング後に「癒された」と感じるクライアントは多いものです。 それは、決して評価されない安全な空間で、これまで隠してきた心の傷や弱み、さらにはエゴや欲まで、ありのままの自分を受け入れてもらえるという、安心と信頼があるからこそです。 あくまでもサーベイは、より深い対話への入り口です。社員のエグゼクティブプレゼンスを高めるためには、信頼関係を築き、一人ひとりの心の奥底に寄り添うことが大切です。そうすることで初めて真の課題を捉え、解決策を見出すことができるのです。 ここまで読んでいただき、ありがとうございました。今回は組織サーベイ編第二弾でした。コーチングの事例が少しでも皆さんのチームビルディングのお役に立つことができれば、嬉しいです。 今後も私のコーチングセッションの体験談やコーチングのテクニックをお伝えすることで、みなさんが組織のリーダーとして活躍するための参考になればと思っています。不定期にはなりますが、次回の投稿もぜひお楽しみに。