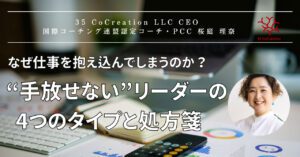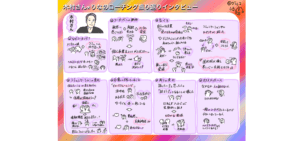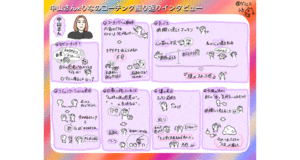Rebranding Story2:「35 CoCreation」は「Coaching Leaders Japan」へと生まれ変わります
2025年5月1日
2025年5月1日、35 CoCreation合同会社はCoaching Leaders Japan(コーチング・リーダーズ・ジャパン)へと社名を改めます。創業から5年という節目を迎え、私たちの存在意義を改めて見つめ直した結果、新たな決意を社名に込めました。 https://coachingleaders.jp/column/rebranding-story-1/ そしてこのタイミングで、会社におけるビジョン・ミッション・バリュー(VMV)も新たにしました。今回のnoteでは、なぜ私たちが社名やVMVをアップデートするに至ったか、またそこに込めた想いを共有します。 目指すは「リーダー」から「コーチングリーダー」への進化 これまで「ヒトのパラダイムシフトを起爆する」をミッションに掲げていた私たち。つまり、コーチングによる対話を通して、人々の視点を変える「起爆剤」となることを目指していました。 しかし、今回改めて深く考えた結果、私たちが目指すのは、単に「パラダイムシフト」を起こすだけではないと気づきました。大切なのは、変化の火種を灯した後、人々が自ら行動を起こし、持続的な成長を実現できる世界を創り出すこと。そのためには、人々の「在り方」そのものを進化させる必要があると考えたのです。 単に「視点が変わった」という変化で終わらせるのではなく、人々の内面から変革を促し、その影響が長く続き、再現性を持って自走できる状態を生み出す。そこまで見届けることが、私たちの役割だと考えました。 新しい社名「Coaching Leaders Japan」に込めた意味 新しい社名は「Coaching Leaders Japan(コーチング・リーダーズ・ジャパン)」としました。 私たちが目指すのは、全ての「リーダー」が「コーチングリーダー」へと進化する世界です。 組織の上層部数名にコーチングを施すだけでは、組織全体の変革は望めません。 部下と本音で語り合い、互いに成長を促し合える関係性。上からの指示に疑問を持ち、必要な場合には積極的に意見できる勇気。このような組織の文化と在り方を創り出せるのは、上に立つリーダーの「在り方」であり、組織をつくる一人ひとりの「在り方」です。 「在り方」を見つめ直したリーダー自身が、コーチングスキルを身に着けて、組織内に質の高い対話を浸透させること。これこそが、組織を劇的に進化させる鍵であると、私たちは確信しています。 新ビジョン 私たちがヒトの「在り方」にこだわるのは、VUCAとも言われる複雑化する社会の中で、従来の「やり方」だけでは通用せず、「在り方」つまり価値観や考え方、行動の基盤となる判断軸が、これまで以上に重要になると確信しているからです。 地球温暖化、資源枯渇、パンデミック。一つの企業や国だけでは解決できない問題を前にして、自分たちの利益だけを追求する利己的な判断は、たとえ一時的には有効でも、長期的には破綻を招く可能性があります。持続可能な発展のためには、他者との共存や将来を担う世代への責任といった、より広い視野に立った勇気ある決断ができる成熟した精神が欠かせません。 だからこそ、私たちは互いに支え合いながら進化できる人材を育成し、これからの未来を創っていきたいと思っています。 新ミッション ミッションには以下の4つを掲げました。 ①Creating Safe Spaces for Authenticity (本当の自分を表現できる安全な場を創る)-わたしたちは、個人と組織が、安心して鎧を脱ぎ、本音や真実、過去の経験を共有し、新たな可能性を見出せる場を創出します。 「会社で本音を語るのは無理だ」 多くの人がそう思い込んでいるかもしれません。 確かに、利害関係、誤解への恐れ、立場や職を失う不安、周囲からの評価など、様々な要因が複雑に絡み合って、組織の中で本音や真実を話すことを難しくしています。 しかし、本音を隠したままの働き方では、組織の成長は頭打ちになるでしょう。本当に重要なことを話さなければならない人が沈黙したり、権力を持つ人が表ではなくて裏で不透明な動きをしたりすることは、組織にとっては大きなダメージになります。 だからこそ、誰もが安心して鎧を脱ぎ捨て、本音で語れる環境を構築すること。それを私たちの第一のミッションに掲げました。 ②Harnessing Curiosity as a Catalyst(好奇心を原動力にする)-わたしたちは、ビジネスシーンにおける好奇心(Curiosity)の力を信じ、引き出し、成長と変革の原動力として活用する文化を広めます 相手に興味を持つ。自分自身にも好奇心を向ける。そして、「今までのやり方を180度変えたら、何か面白いことが起こるかもしれない」と、好奇心を使って新たな道を切り拓く。 私たちは、好奇心の力を心底信じています。根底にあるのは、「人は誰でも好奇心を持っている」という信念です。私たちは心理的に安全な空間で一人ひとりと向き合うことで、それぞれが元来持っている好奇心を引き出します。そして、その好奇心を成長の原動力に変え、組織の変革を加速させます。 ③Embracing Struggles as Pathways to Growth (困難を成長への道と捉える)-わたしたちは、困難や葛藤を共に受け入れ、それを成長の糧に変える道筋を示し、組織と個人が自律的に進化できるよう寄り添います 私たちは一人ひとりの悩みや苦しみを、敬意を持って受けとめ、その存在を認めるところから始めます。なぜなら、コーチングが求められるのは、たいていの場合、これまで上手くいっていたことが上手くいかなくなったり、進むべき道が見えなくなったりした時だからです。 だからこそ、その困難を単なる障害として捉えるのではなく、成長の機会として一緒に探求し、乗り越えるための道筋を示します。 ④Guiding Transformation with Clarity and Empathy(明確さと共感で変革を導く)-わたしたちは、灯台のような存在として、明確な指針を示し、時には見守り、変革への旅路を支えます。国際ビジネスで培った実践知と共感力を活かして、真の変革を共に実現します 私たちはクライアントに常に関わり続けるのではなく、必要な時にいつでも戻ってこられる、温かい灯台のような存在でありたいと思っています。 「ちょっと道に迷ってしまった」「また方向性を見失ってしまった」 そんな時、安心して戻ってこられる場所。私たちは、クライアントの変革への旅路を、温かく見守り、支え続けるパートナーでありたいと思っています。 新バリュー 最後に、アップデートしたバリューがこちらです。 恥じらいや隠したいと感じる部分こそが、実は変革の鍵を握っていると私たちは信じています。だからこそ、クライアントが勇気を出して自己開示する瞬間を、最大限の敬意をもって受け止めるし、クライアントが「ここなら大丈夫」「ここなら受け入れてもらえる」と感じられるような、神聖なパートナーシップを築くことを目指します。 そしてどんな状況でも逃げない、寄り添う存在として、クライアントの挑戦を支えます。 変化することは個人にとっても、もちろん組織にとっても、簡単なことではありません。私たちはその困難さを、十分に理解しています。 私たちの専門領域は「人」です。だからこそ、クライアントの「話を聞いてほしい」「受け入れてほしい」という切実な思いに耳を傾け、変革の過程で生まれる感情やありのままの人間的な部分に向き合いたい。 理屈や戦略だけではなく、人間的な感情の部分に寄り添い、共に歩むことを大切にしたいと思っています。 「コーチングが当たり前」の世の中を目指して 長文にお付き合いいただきありがとうございました。 「なぜ組織に向き合うことが大事なんだっけ?」 「コンサルティングではない、コーチングの意味って?」 「私たちだからこその役割とは?」 そんな根源的な問いに立ち返りながら、言葉にするのは、なかなか大変な作業でした。ですが、とことん議論して対話して言葉を「ああでもない、こうでもない」と転がしながら言語化をやりきったことで、自分たちの目指す世界に対する解像度が大きく上がったように思います。 私たちの願いは、コーチングが特別なものではなく、誰もが日常で実践できるスキルになること。そして、あえて「コーチ」と呼ばれる特別な職業がなくなる世界を実現することです。 「コーチングが当たり前」の世の中とは、人々が自らの可能性を最大限に引き出し、組織が自律的に進化し続ける、そんな持続可能な未来だと私たちは信じています。 「うちの組織は、コーチングが根付いているから、もう大丈夫。」 そう言われる未来を目指して、ここからまた歩み始めます。