「社員への思いやり」が組織の成長を止めていた。マリンアクティビティ事業経営者の選択
2024年11月18日
株式会社 なんのこれしき
| 業種 | マリンアクティビティ事業 |
|---|---|
| 導入の背景 | マネジメントに限界を感じていた |
| 導入後の効果 | 組織の主体性が高まり、少数精鋭による高成果なチームへと移行 |
マリンアクティビティ事業を軸に会社を経営する小金沢昌博さんは、起業当初に思い描いていた理想の会社像と、現在の現実とのギャップに苦悩し、Coaching Leasers Japanの前身、35 CoCreationのコーチングプログラムを受講されました。
セッションを通じて、どのようにそのギャップを埋めて組織を成長させていったのか、小金沢さんご自身の言葉で振り返っていただきました。
コーチングを受けようと思ったきっかけ
ーコーチングを受けようと思われたきっかけについて教えてください。 元々の桜庭さんとのご縁や、コーチングに対する好奇心もさることながら、コロナ禍で将来に対する不安が増し、時間的な余裕もできたことが、コーチングを受ける大きな後押しになりました。
当時、私は事業経営に思い悩んでいました。個人事業主として立ち上げた事業を法人化し、2年目で売上は倍以上と大幅に伸びましたが、マネジメント経験はなく、従業員を上手くリードできずにいました。プレイヤーとして現場を回し、売り上げを立ててきた自負から、今思えば知らず知らずのうちに従業員を管理し、こき使うような働き方を強いてしまったのかもしれません。その結果、売り上げは上がってもスタッフの定着率は低く、働きがいのある職場とは言えませんでした。
「自分が起業した当初の目的はこれだったのだろうか」と自問自答し、今後のあり方を見つめ直す必要性を感じていました。
ー起業したきっかけは?
ダイビング業界に対する、ある種の反骨精神とでも言うべきでしょうか。ダイビングは、人々の人生を大きく変える素晴らしい体験を提供できる仕事です。一方で、人の命がかかるため、安全管理は常にする必要があるのにも関わらず、私が事業を立ち上げた当時は特に、業界で働く人の待遇は決して良いとは言えませんでした。それが、どうしても納得できませんでした。
とはいえ、「業界を変えてやろう」といった壮大なビジョンを掲げていたわけではなく、「自分だったらこんな働き方は嫌だ」というシンプルな気持ちから、個人事業をスタートしたのです。だからこそ、思い描いていた理想と現実の間で、どうしたらいいのかと立ち止まってしまったのです。
悩んだ結果、4年目に売上を意図的に大幅に削減し、従業員に無理を強いる経営から脱却することを決意しました。正直、不安は大きかったです。でも、そのまま続けることは、どうしても自分の感情が許さなかった。桜庭さんにコーチングを受けてみませんかと言われたのは、ちょうどこの頃でした。
コーチングを受けての気づき
ー実際にコーチングを受けてみて、どんな気づきがありましたか?
「自分がどうありたいか」を見つめ直す機会を与えてもいました。自分の感情を整理し、言葉にする練習を重ねることで、少しずつ言語化できるようになりました。
そしてコーチングやプロのサポートを受けながら、最終的には会社の「MVV」を策定することができました。私たちの会社が掲げるMVVは、シンプルに「愛」です。愛に満ちた会社として、100年という長い歴史を築きたいと考えています。
そのために100年後の未来を想像し、改めて自分自身を見つめ直したところ、私個人の能力や実績は、組織の存続のためにはそれほど重要ではないということに気づきました。この気づきをきっかけに、不要なものを手放し、より本質的なことに集中できるようになりました。小さな企業だからこそ、トップダウンで物事を進め、目先の売上を追求することも可能です。
しかし、組織として長く存続するためには、チーム全体で「本当に大切なことは何か」を常に意識し、本質的な問題解決ができるチームを作り上げたいと考えています。そういう対話の場は、コーチングで意識が変わってからは非常に増えましたね。
ーコーチングの中で記憶に残っている対話はありますか?
桜庭さんがよく使われる「いいか悪いかではなく」という言葉は、特に印象に残っています。人は、生まれ育った環境や価値観によって、物事を判断しがちです。そのため、「これは悪い」と決めつけるのは簡単ですが、状況や背景によって評価は変わるものです。
「良い」か「悪い」という二元論で判断されると、人は意見を言い出しにくくなります。しかし、一旦その判断を保留し、みんなで一緒に考えていくことで、私たちの会社でも「〇〇さんの考え方はすごいな」「それは私にはできないな」など、お互いの意見を尊重し、建設的な議論ができるようになりました。
まずお互いを受け入れることで、心理的安全な環境が整って対話の質が上がりましたし、組織としてもうまく回り始めたと感じています。

社内の変化
ー小金沢さんがコーチングを受けたことで、ほかにも会社の中での変化はありますか?
最近、大きな変化がありました。新卒4年目の女性社員から、「小金沢さんが業務を手放さないことが、組織の成長を妨げている」と指摘されたのです。正直、かなり驚きました。私は、彼女の優秀さを認めており、結婚もしていることから、なるべく早く帰宅してほしいという思いもあり、思いやりからサポートしているつもりでした。しかし、彼女にとっては、仕事を最後までやり遂げることのほうが重要だったのです。
私の考えと彼女の考えの間に大きな隔たりがあったことに気づき、何度も話し合い、9年間育ててきたダイビング事業部を彼女に託し、彼女が主体的に事業を運営して、私はサポートに回るという新しい体制に移行することを決めました。
もちろん、将来的に事業部を後進に任せることは考えていましたが、10年くらいはかかるだろうと考えていました。それがわずか4年で、スタッフから具体的な言葉として出てきたのです。理想と現実のギャップを知り、ショックでもありましたが、組織の成長が大きく加速していると感じる印象深い出来事でもありました。ー信頼関係があって率直に意見交換できるからこそ、チームとして目指す方向を共有し、より良い判断ができている素敵なエピソードですね。
そこは本当にコーチングのおかげですね。チームで目標に向かっていく上で、社長として、会社全体への情熱は欠かせません。ただ事業部という単位で見ると、有り余る情熱が過剰に影響を与え、周りのメンバーのやる気をそいだり、かえって弊害になる場合もあるかもしれません。
重要なのは、それが“いい悪い”ということではなく、バランスを適切に保つこと。コーチングのおかげで、より広い視点から物事を捉えられるようになりました。事業部を後進に託したからといって、私の情熱がなくなるわけではありません。むしろ、私のエネルギーを少し抑えることで、スタッフのモチベーションが向上し、組織全体の活性化につながるならば、私は別のところで情熱を燃やせばいい。チームとして、会社として、一つフェーズが進んだことを実感しています。
ー事業経営にどのような変化がありましたか?
コーチングを受けて、昨年はコロナ前の最高売上を達成しました。以前は、アルバイトを数人雇って、指示や管理中心の働き方をしていましたが、現在は私・妻・社員の3人で、それ以上の成果を上げることができています。
とはいえ、コーチングが全てを変えるとは思いません。大切なのは、自ら変わりたいという強い意志とわき上がる好奇心、それを後押ししてくれるコーチの存在です。
人が変われば、組織にも必ず影響を与えます。しかし、個人が変わるだけでは、組織全体の成長にはつながりません。組織の理想と個人の理想を結びつけ、お互いを尊重し合いながら、組織全体が共に成長していくことが重要だと実感しています。
私たちは3人の小さな会社だからこそ、柔軟に変化できます。一人ひとりの意識改革が、組織の文化を根底から変えていくと信じています。現在、妻もコーチングを受けており、来年には社員にも受けてもらう予定です。
コーチングは個人の成長を促しますが、組織全体の変革には、さらに別の仕組みが必要です。その仕組みを創出していくのは、コーチングを受けた私たち一人ひとりの役割です。このプロセスを楽しみながら、大きな成果を上げていきたいと思っています。
関連記事
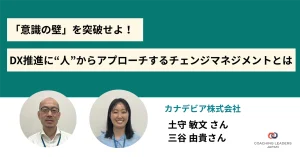
カナデビア株式会社
DXを成功に導く「チェンジマネジメント」──カナデビア社の挑戦
従業員数: | 業種:環境設備のプラントメーカー
課題と効果:現場に浸透しなかったDXが、アーリーアダプターを軸に意識が変革
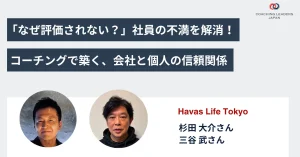
Havas Life Tokyo
急成長組織が直面したマネジメントの壁と変革への挑戦
従業員数:約50人 | 業種:広告代理店
課題と効果:組織全体として同じ方向を向いて進むのが難しかった組織が、本音で語り合える心理的安全性が生まれ、現場での意識が変化
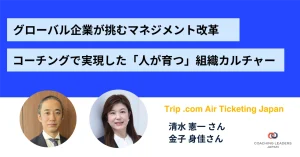
Trip.com Air Ticketing Japan
グローバル企業が挑むマネジメント改革 | Trip.comがコーチングで実現した「人が育つ」組織カルチャー
従業員数:*** | 業種:旅行業
課題と効果:“対症療法”的になりがちだった研修が、「できていることに目を向ける」という文化づくりに
